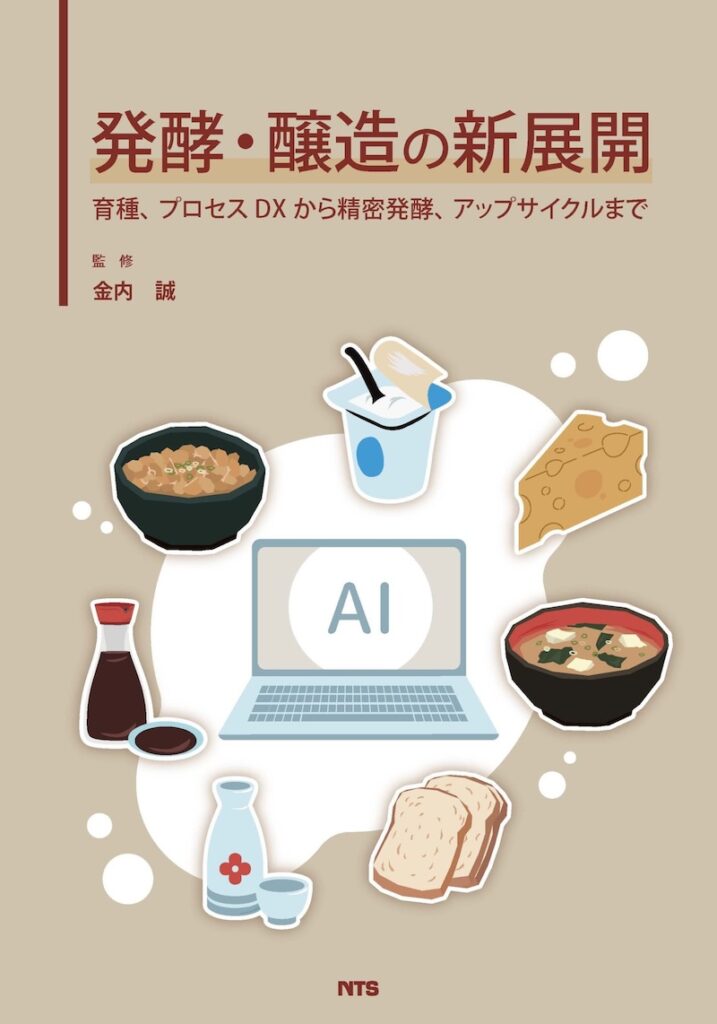発酵科学の最前線を伝える専門書に「アスリート向け高タンパク質デニッシュパン」の開発事例を寄稿【発酵醸造食品機能性研究センター/スポーツサイエンスコース】
2025.08.01
科学が“おいしい”をつくる――新刊が描く発酵・醸造研究の新たな可能性
味噌や醤油、日本酒といった伝統食品のイメージが強い「発酵・醸造」。実は今、その技術はスポーツや医療、環境、ITなどの分野と結びつきながら大きく進化しています。
2025年7月に刊行された専門書『発酵・醸造の新展開 ~育種、プロセスDXから精密発酵、アップサイクルまで~』(NTS出版)は、そうした最先端の研究や事例をまとめた一冊です。
同書の第2章「新しい発酵食品の開発」の第2節「スポーツ×発酵・醸造―アスリートデニッシュの開発事例」において、発酵醸造食品機能性研究センター(※1)の松永敬子教授(当センター副センター長/本学経営学部スポーツサイエンスコース)と島 純教授(当センター客員研究員/福島大学 食農学類・本学名誉教授)が近年の取り組みについて寄稿しました。
具体的には、発酵技術を活用したアスリート向け高タンパク質デニッシュパン(※2)の開発の背景として、スポーツによる地方創生進む中、とりわけスタジアム・アリーナ開発において発酵醸造(ビール醸造所やパン工房)が注目されていること。そうした中、2023年7月に山梨県にて開催された「日本スポーツ産業学会第32回大会 アイディアコンペ」において、本学スポーツマネジメント研究室が提案した野生酵母使用のデニッシュパンが、学会長賞と山梨県知事賞を受賞したこと(※3)を契機に、同年8月にやまなしスポーツエンジン(山梨県)と「アスリート等向け食品の開発業務委託契約」の契約に至った経緯があります。
また、デニッシュパンの開発過程においては、製パンに適した酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)を山梨県内の野生環境から約300試料を採取して分離・同定・解析によって選定した上で、手作業で少量培養を実施したこと。さらに、アスリートの疲労回復につなげるため、石原健吾教授(当センターセンター長/本学農学部)の協力を得て、高タンパク質となるように材料の配合やパンの形状等についても検討を重ねたことなどを紹介。発酵科学と栄養学、そしてスポーツマネジメントの専門分野が融合する実践的なモノづくりのプロセスを描いています。

この本は研究者や開発者向けに書かれた専門書ですが、「発酵って、なんか面白そう」「ものづくりに関わる仕事に興味がある」という人にも、ヒントを与えてくれる内容が詰まっています。
日常の中にある「発酵」の可能性を、ぜひのぞいてみてください。
【補註】
(※1)龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センター
滋賀県の発酵醸造産業を支援することを目指して2021年度に開設。発酵醸造に有用な微生物の収集とデータベースの構築、およびそれらを活用した応用研究の展開を目的として研究活動を展開している。2021-2023年度は発酵醸造微生物リソース研究センターの名称で活動し、2024年度より現在の名称に改称。「微生物の有用機能を介した発酵醸造学とスポーツ栄養学の融合とマネジメントによる滋賀県域における応用展開」をテーマに、研究体制を拡充して、より学際的に研究を推進している。
https://hakko.ryukoku.ac.jp/
(※2)発酵技術を活用したアスリート向けのデニッシュパン・関連ニュース:
龍谷大学 松永敬子研究室とやまなしスポーツエンジンが共同開発 『YAMANASHI SDGs FORUM 2024』にて山梨県産のぶどう野生酵母アスリートデニッシュ試作品の試食会を実施 当日は共同出展ブースの試食会に約700名参加(2024.03.11)
(※3)山梨県との委託契約による実証事業・関連ニュース:
松永研究室が日本スポーツ産業学会にて「日本スポーツ産業学会学会長賞」と「山梨県知事賞」をW受賞【経営学部・スポーツサイエンスコース】(2023.08.04)